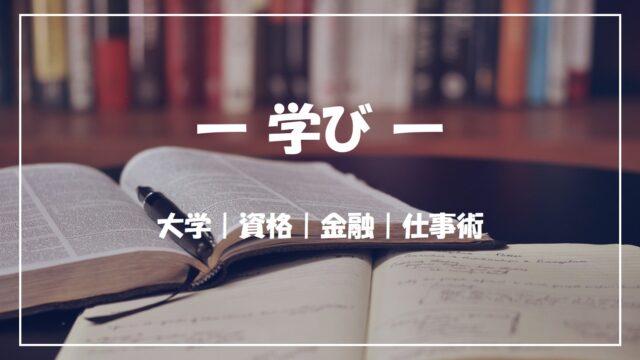会社で活躍できていないと悩んでいる
仕事ができる人になるための考え方を教えて!
上記のようなお悩みを解決します。
✓ 本記事の内容
・社会で求められる能力は「解決力」と「創造力」である理由
・社会で役立つのは「数学」と「群像の感覚」である理由
✓ 本記事はこんなかたにオススメ
・会社でいまいち評価されていない
・学歴の割に仕事ができないと思われている
・社会で役に立つスキルや考え方が知りたい
林先生は社会に出て役に立つのは、圧倒的に「数学」だと言っています。
それはなぜか?
理由は、社会で求められる解決力と想像力を磨くのには「数学的な論理的思考」が役に立つからです。
そこで今回は
「社会で求められるのは解決力と創造力である理由」
「社会で役立つのは数学と群像の感覚」
について解説します。
この記事を読めば、社会で活躍できる人材になるためのスキルと考え方がわかります。
ぜひ参考にしてみてください。
社会で求められる能力は「解決力」と「創造力」
「解決力」が求められる理由
なぜ解決力が必要なのか。
理由は、すべての仕事は「誰の」「どんな問題」を解決するかに集約されるからです。
例えば、会社で「プログラミングを学べる教育事業」を始めるとします。
この例でいえば、
「誰の:プログラミングを学びたいと思っている人の」
「どんな問題:勉強するきっかけや学習時のサポートを受けたい」
を解決することで「プログラミングを学べる教育事業」が成り立ちます。
仮にあなたが、学習レベル別に教育者を採用する仕事(問題)にアサインされたとします。
学習レベル別に教育者を採用できなければ、ある学習レベルの設定は諦めなくてはいけません。
これでは、「誰の:プログラミングを学びたいと思っている人の」の部分で、
学習レベルが限定されてしまい、競合他社に負けてしまうリスクがあります。
そうならないように、アサインされた仕事を確実に解決していかなければなりません。
この他にも、どの年齢層をターゲットにするのか、学習レベルはどう設定するのか、教育者はどう配置するべきかなど、解決すべき課題は山積みです。
このような課題ひとつひとつを解決していかなければ、
「プログラミングを学べる教育事業」を成功に導くのは難しいでしょう。
会社は組織ですので、個人一人ひとりが、課題を確実に「解決する力」を発揮して、
初めて会社としての「プログラミングを学べる教育事業」の成功があるのです。
ゆえに、会社に属する個人は、共通して「課題を解決する力」が求められているのです。
「創造力」が求められる理由
創造力が必要なのは、なぜか?
理由は、新しいものを生み出さなければ、会社も個人も成長しないからです。
Apple社がiPhoneを初めて世の中に発表したときは衝撃的でしたよね。
iPhoneをはじめとするスマホが世に生み出されてからは、誰もが簡単にネットで多くの情報にアクセスできる時代になりました。
凄まじい進歩(成長)ですよね。
それがApple社も既存のガラケーを一生懸命に開発していたとしたら、いまのようにアメリカを代表する大企業には成長していなかったことでしょう。
このように新しい何かを生み出さなければ、会社が大きく成長することはありません。
それは個人である私たちにもいえます。
同じ事務作業を延々と繰り返しているだけで、成長はあると思いますか?
ないですよね。
同じ事務作業の中でも、
エクセルでマクロを作って作業を効率化したり、
その浮いた時間で新しい企画を上司に提案したりと、
何か新しい価値やモノを創造していかなければ、成長はありません。
逆にいえば、新しい価値を創造できれば、個人も会社も成長できるようになっています。
そういう意味で、何か新しい価値を生み出す「創造力」が求められているのです。
社会で役立つのは「数学」と「群像の感覚」
解決力と想像力を鍛えるには、
どうすれば良いの?
数学的な論理的思考と
群像の感覚が必要です!
それぞれ解説していきます!
数学的な論理的思考ができれば、課題解決がしやすい
それでは一体なぜ社会で役立つのは数学なのか?
その理由は、
①課題を整理して考えるときに便利
②仮説を立てて最短ルートで課題解決するのに便利
だからです。
理由①:課題を整理して考えるときに便利
ああああああああ仕事ができる
あああああああああああ|
ああああああああ② |ああ①
あああああああああああ|
勉強ができないーーーーーーーーー勉強ができる
あああああああああああ|
ああああああああ④ |ああ③
あああああああああああ|
ああああああああ仕事ができない
世の中の人は、この図のどれかに当てはまるはずです。
①勉強ができて、仕事ができる (←最高)
②勉強はできないけど、仕事はできる (←良い)
③勉強はできるけど、仕事ができない (←微妙)
④勉強はできないし、仕事もできない (←最悪)
「中卒なのに仕事めちゃくちゃできるよね」という人は②に当てはまるし
「あの人は東大でてるのに仕事できないね」という人は③に当てはまります。
確かにこの図をみると中学生のときに習った「直線と直線の交点を求める方法」を思い出す方もいらっしゃるかもしれません。
ただ使い方によっては、このように何か課題を整理するのに非常に役に立ちます。
理由②:仮説を立てて最短ルートで課題解決するのに便利
「A条件かつB条件であれば、仮説Cが成り立つ」といった自分なりの仮説を立てるのに数学的な論理的思考が役に立ちます。
例えば、XXX大学に合格する課題があったとします。
世の中にはたくさんの勉強法があふれていますよね。
大学受験でいえば
「数学は青チャートを繰り返しやりなさい」
「数学は大学への数学をやりなさい」など
同じ数学でもオススメの問題集は様々だったと思います。
そこから
「自分が目指すXXX大学に合格した人は、
A条件:青チャートをやっていた人が多かったな」とか
「A大学を目指すならどの問題集が良いかをいろいろな大人に聞いたけど、
B条件:青チャートと答える人が多かったな」というような形で、
自分で分析すると「Cという仮説:XXX大学に合格するには青チャートが良い」
という仮説が立てられると思います。
このように「A条件かつB条件であれば、仮説Cが成り立つ」といった自分なりの仮説を立て検証する」思考をするのに数学的な論理的思考が役に立ちます。
そこから、その仮説を実証するために1年間勉強してみて、成果が出るか検証してみる。
このように、自分で仮説を立てて検証しながら、自分なりの正解を導くことができれば、合格できる可能性が高まってくるとは思いませんか?
ただ闇雲に仕事をするよりも、自分なりの仮説を立てて進めていったほうが最短ルートで課題解決ができるとは思いませんか?
群像の感覚をもてば、評価されやすい
群像の感覚とは、全体の中での自分の強みとは何か?を俯瞰する感覚です。
群像の感覚をもてば、評価されやすいのはなぜか?
その理由は、
①自分の得意領域で勝負したほうが評価されやすい
②周りからみた自分を客観視できれば、強みがみえてくる
からです。
理由①:自分の得意領域で勝負したほうが評価されやすい
何かを解決するにしても、新しい価値を創造するにしても、自分の得意領域で戦ったほうが有利に決まっていますよね。
それが数学が苦手なのに経理をやっていたり、法律が苦手なのに法務にいたりという方が多くいらっしゃるように感じます。
よく小さいときには、苦手を克服しましょうと言われましたよね。
ただ、弱みはゼロにすることはできても、大きくプラスにすることは難しいです。
社会全体からみて「自分の強みは何か?」を考え、自分の勝てる環境で勝負しましょう。
そうすれば、同じ難易度の課題でも難なくクリアできたり、成果も評価されやすいです。
理由②:周りからみた自分を客観視できれば、強みがみえてくる
例えば、海外留学の経験があれば、実際はしゃべれなくても「英語しゃべれるんでしょ?」と聞かれることがあるでしょう。
海外の方を対応してと仕事で求められることもあるかもしれません。
それは、ある種チャンスです。
周りから英語ができる人と期待されているのですから、そのスキルを磨けば良いのです。
そういった周りからの期待に応えることをきっかけに、自分の強みも見えてくるものです。
最後に
最後におさらいです。
今回は
「社会で求められるのは解決力と想像力である理由」と
「社会で役立つのは数学と群像の感覚」
について解説しました。
みなさんも、この記事を読んで、社会で活躍できる人材になるためのスキルと考え方を身につけるきっかけをつかみましょう。
■社会で求められる能力
解決力とは、何かの問題を解決できる能力
すべての仕事は「誰の」「どんな問題」を解決するかに集約される
創造力とは、何か新しいものを創造できる能力
新しい価値を創造できれば、個人も会社も成長できる
■社会で役立つのは「数学」と「群像の感覚」
数学的な論理的思考ができれば、課題解決がしやすい
・課題を整理して考えるときに便利
・仮説を立てて最短ルートで課題解決するのに便利
群像の感覚をもてば、評価されやすい
・自分の得意領域で勝負したほうが評価されやすい
・周りからみた自分を客観視できれば、強みがみえてくる
こちらでは、林先生に学ぶ【仕事ができる人特徴5選】を紹介しています。
人はできない言い訳とやらない理由を見つけ出す天才です。
仕事ができるようにならないあなた。
本記事を読めば、仕事ができる人に近づくことができます。
林先生に学ぶ【仕事ができる人特徴5選】人はできない言い訳とやらない理由を見つけ出す天才